

歯垢(デンタルプラーク)とは、食べ物のカスが歯の周りに付着したものだと思われがちですが、その正体は意外と知られていません。実は、歯垢の8割が水分で、それ以外は口の中の細菌や細菌から出た代謝物によってできています。
ネバネバとした粘着質の歯垢には、1ミリグラムあたり1億個以上の細菌が存在するといわれ、その中には健康な口内に存在する常在菌もあれば、そうでない病原細菌もあります。特に、歯周病の原因となる細菌は、嫌気性といって酸素を好まない性質のため、歯と歯ぐきの間などで繁殖を繰り返すのです。

歯垢(デンタルプラーク)は、歯が見えている歯冠部に付着する「歯肉縁上プラーク」と、歯と歯ぐきの間の歯周ポケットの中に付着する「歯肉縁下プラーク」の2つに分けられ、歯と歯ぐきの境目にできる歯肉縁上プラークや、歯肉縁下プラークが歯周病の原因になるといわれています。
毎日、しっかり歯磨きをしているつもりでも、歯と歯の間や奥歯の噛み合わせ、歯と歯ぐきの境目などは、歯ブラシが届きにくいことから歯垢が付着したままの状態に。その磨き残しによる歯垢が付着している部分で、歯周病の症状が現れるのです。
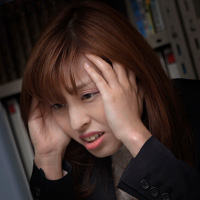
歯ぐき・セメント質・歯根膜・歯槽骨などの、歯を支える組織で起こる病気『歯周病』の中でも、歯肉炎は初期段階の状態。磨き残しや歯周ポケットに溜まった、歯垢の中で繁殖している細菌が出す毒素によって歯ぐきが炎症を起こすことで、腫れや出血の症状が現れるのです。
さらに歯周病には、歯並び・噛みあわせが悪い場合や歯ぎしりの習慣、また、ホルモンの影響・ストレス・疲労・喫煙などの、間接的な原因があるといわれています。そのため、歯周病を予防するためには、歯垢除去だけでなく、口腔内の環境や生活習慣への注意が必要となります。

歯周病といっても歯肉炎は軽度のため、歯磨きをしっかりすれば完治することができるのですが、歯の裏側や親知らずのような奥歯など、目が届きにくい部分は歯ぐきの腫れなどを見落としがち。さらに、痛みなどの自覚症状が少ないことから気付きにくいのです。
歯肉炎は放っておくと症状がどんどん進行して、最終的には手の施しようのない状態になってしまいます。そうならないためには、普段からこまめに歯ぐきの色や腫れ、出血などの状態をチェックして、歯垢を残さないための歯磨きや歯科での定期的なクリーニングをおすすめします。
Copyright (C) 2014 デンプラ読本 All Rights Reserved.